【遺言の作成】遺言執行者は立てる必要があるか?
遺言書を作成しようと考えたときに、遺言の内容として「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者は、遺言書の内容に従い、故人の意思を実現する役目を担います。遺言を作成する際に必ず遺言執行者を立てる必要があるわけではありませんが、立てることで多くのメリットがあります。
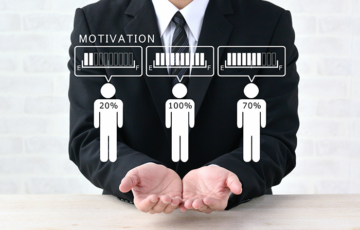 遺言執行者
遺言執行者
遺言書を作成しようと考えたときに、遺言の内容として「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者は、遺言書の内容に従い、故人の意思を実現する役目を担います。遺言を作成する際に必ず遺言執行者を立てる必要があるわけではありませんが、立てることで多くのメリットがあります。
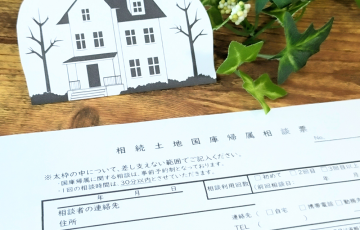 相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度
近年、相続によって取得した土地を「使い道がない」「管理が負担」「売却もできない」といった理由で手放したいと考える方が増えています。こうした背景を受け、2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。この制度は、一定の条件を満たすことで、相続や遺贈により取得した土地を国に引き取ってもらえる仕組みです。
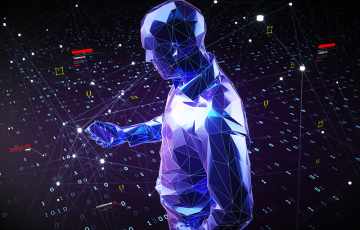 デジタル遺産
デジタル遺産
終活の一環として注目されているのが「デジタル遺産」の整理です。デジタル遺産とは「故人が生前に利用していたインターネット上の財産や情報」のこと。具体的には、SNSアカウント、ネット銀行や証券口座、電子マネー、クラウドに保存された写真や文書、サブスクリプション契約などが含まれます。
 地面師詐欺
地面師詐欺
地面師詐欺とは、他人の土地をあたかも自分のものであるかのように偽り、無関係な第三者に売却してお金をだまし取る犯罪です。この詐欺は巧妙な手口と組織的な犯行が特徴で、被害額はときに数十億円に上ることもあります。司法書士としてこの恐ろしい犯罪について、その手口、対策、そして法的な観点から解説します。
 相続登記
相続登記
日本全国には、登記がされず「誰の土地かわからない」状態の土地が多数存在します。これは、相続が発生しても登記がされないまま放置されてきた結果です。こうした「所有者不明土地」は、公共事業や防災対策、地域活性化の妨げとなり、社会的な課題となっていました。
 相続手続き
相続手続き
『「相続放棄」と「遺産分割」ってどう違うか分からない!』『相続が発生したら、まずは遺産分割をするんだよね?』そう思っていませんか?実はその前に確認しておくべき大切な選択肢があります。それが「相続放棄」です。この記事では、「相続放棄」と「遺産分割」の違いを、初めて相続に直面する方にもわかりやすく解説します。
 相続順位
相続順位
相続が発生し、亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹が法定相続人になるケースがあります。実際に財産を受け取るかどうかにかかわらず、民法の規定により相続する権利をもつ人を「法定相続人」といいます。民法では被相続人が遺言を残していない場合、法定相続人になる人の範囲と順位が定められています。
 相続登記
相続登記
相続登記が義務化になり、ご自身で登記をすることを検討する方もいるでしょう。被相続人が所有するすべての不動産は、相続登記が必要です。しかしながら、時には見落とされてしまい登記されない不動産もあります。登記漏れの不動産はあとから見つかると、手続の負担が増えてしまうので、原因を知ることで漏れを防げるようにしましょう。
 住所変更登記の義務化
住所変更登記の義務化
令和8年4月1日から不動産の所有者は氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられることになりました。これは所有者不明の土地の解消対策として施行されるものです。施行前の住所変更でも未登記であれば対象となり、「正当な理由」がなく申請を怠った場合には、5万円以下の過料が科せられることがあります。
 代償分割
代償分割
不動産など現物を相続した相続人から、ほかの相続人に支払う代償金は、相続人自身の財産から支払う場合もあります。一度に代償金を支払うことができない場合、相続人の間で合意があれば分割で支払うこともできますが、のちに未払いが生じた場合は、ほかの相続人との間でトラブルに発展する可能性があります。
 代償分割
代償分割
「代償分割」とは、相続における遺産分割方法のひとつで、「特定の相続人が分割するのが困難な遺産を相続し、それ以外の相続人が遺産を取得した相続人から代償金を受け取る」という内容の分割方法のことをいいます。不動産を相続する人にとってのメリットは、土地や自宅などの遺産をそのままの形で取得できることです。
 遺産分割協議
遺産分割協議
被相続人が遺言書を遺すことなく相続が開始すると、法定相続もしくは相続人全員による遺産分割協議を行なうことになります。しかし、被相続人の前妻の子や甥・姪など面識のない方や、疎遠な方も相続人になることがわかった場合には遺産分割協議を始める前に、まずその方と連絡を取らなければなりません。