【相続手続】遺産にマイナスの財産がある場合
亡くなった被相続人に不動産や預貯金のようなプラスの財産だけでなく、住宅ローンや消費者金融からの借金などのマイナスの財産(債務)もあった場合、相続手続きにあたって債務はどのように扱われるのでしょうか。
 遺産分割協議
遺産分割協議
亡くなった被相続人に不動産や預貯金のようなプラスの財産だけでなく、住宅ローンや消費者金融からの借金などのマイナスの財産(債務)もあった場合、相続手続きにあたって債務はどのように扱われるのでしょうか。
 遺言執行者
遺言執行者
「亡くなった人の身の回りの整理を始めていたら、遺言書が出てきた」というお話を伺うことがあります。「遺言書を作成しているかどうか、生前に聞いていない」ということは珍しくありません。ここでは亡くなった人が作成した遺言書が見つかった場合の、手続きの方法や流れについて確認していきます。
 相続放棄
相続放棄
亡くなった親に多額の借金や税金などの滞納があったり、誰だかもわからないような疎遠な関係だった人の相続人になってしまったときに、「自分は相続人になりたくない」と考えた時に取る手続きを「相続放棄」と言います。相続放棄手続きは、手続きできる期限や方法が法律で決まっています。またメリット・デメリットがあります。
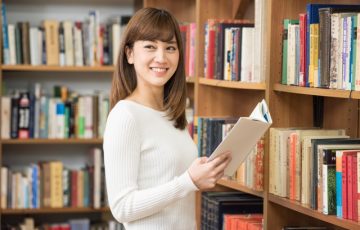 成年年齢引き下げ
成年年齢引き下げ
2022年4月1日に『民法の一部を改正する法律』が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。この民法改正によって、18歳から親権者の同意を得ずに一人で有効な契約ができ、遺産分割協議にも参加できるようになります。一方で、飲酒・たばこ・競馬など法改正前の20歳のままの年齢制限のものもあります。
 遺言執行者
遺言執行者
『希望する相手に、希望通りに財産を分配したい』というを想いを叶えるための手段として、注目されている遺言書。でも、その遺言書の内容を実現させるためには「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を指定しておくと、遺産相続におけるトラブル防止のために重要な役割を果たすことがあります。
 家族信託
家族信託
不動産取引においても、不動産を売却して生活費や施設への入居費用に充てようとするなど、高齢者が当事者として関わる取引が多くなっています。しかし、当事者が高齢者の場合、売却活動開始から売買契約締結・引渡しまでの間に何らかのトラブルが発生するリスクがあります。
 遺産分割協議
遺産分割協議
遺産分割協議書とは遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するものです。遺産分割協議がまとまれば、遺産が相続人ひとりひとりの権利になります。遺産分割協議書とはこの協議の内容を記載した正式な文書です。遺産分割協議書を作成することで、その後の紛争防止や、相続手続きの円滑化に繋がります。
 相続対策
相続対策
遺言書は大きく2つの方法があり、公正証書遺言と自筆証書遺言に分けられ、自分で書いて完成させられる手軽さから、「自筆証書遺言」を選ばれる方が多くいらっしゃいます。しかし、その自筆証書遺言を使って、「相続人が財産分けを進めようと思ったのに手続きが進められない」という事例が見受けられます。
 登記
登記
全国の法務局では、平成26年度以降に毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行なっています。
休眠会社または休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記または事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記がされます。
 遺言
遺言
自分で書いた遺言書「自筆遺言証書」を法務局で保管してくれる制度が2020年7月10日にスタートしました。この制度をきっかけに、多くのお客様から「遺言書を作成したい」というご相談を受けるようになりました。
お客様のご相談に対応して1年が経った今、改めて制度のメリット・デメリットを確認しながら、効果的に利用するための方法をまとめてみたいと思います。
 相続対策
相続対策
最近、相続をあえて「争続」と記載するほど、「相続は揉めるもの」とイメージされています。
些細なトラブルから家族関係が崩壊してしまうなど、取り返しのつかない事態になるかもしれない相続。
どのようなトラブルがあるのかを知り、事前に対策しておくことが必要です。
トラブルのひとつとして挙げられるのが、「相続人間で遺産を隠してているのではないか」と疑ったり、または疑われたりするケースです。
 ■不動産のお話
■不動産のお話
住宅ローンを利用してマイホームを購入したときに、銀行などから設定される『抵当権』。万が一、返済が滞ったときのために土地や建物を担保にとるもので、マイホーム購入の登記と同時に『抵当権設定登記』という登記がなされます。