相続トラブル~兄弟が揉める一番の原因
ある50代の男性Mさんは、妻子と80代の母親と暮らしていました。 Mさんにはお姉さんと弟さんがいて、それぞれ結婚して所帯を構えて、普段からの兄弟間の交流もあり、大変仲も良く、5年前に父親が亡くなった時の相続も円満に問題なく済ますことができました。 母親もそんな子供達の様子をみて、これといった大きな財産も無かったので、 特に相続の準備はしていなかったのです。
 遺言信託
遺言信託 労務管理
労務管理 お役立ち情報
お役立ち情報 税務申告
税務申告 住宅ローン控除
住宅ローン控除 ライフプラン
ライフプラン 災害保険
災害保険 お役立ち情報
お役立ち情報 労務管理
労務管理 労務管理
労務管理 ライフプラン
ライフプラン 軽減税率
軽減税率 相続対策
相続対策 消費税
消費税 労務管理
労務管理 労務管理
労務管理 相続対策
相続対策
ある50代の男性Mさんは、妻子と80代の母親と暮らしていました。 Mさんにはお姉さんと弟さんがいて、それぞれ結婚して所帯を構えて、普段からの兄弟間の交流もあり、大変仲も良く、5年前に父親が亡くなった時の相続も円満に問題なく済ますことができました。 母親もそんな子供達の様子をみて、これといった大きな財産も無かったので、 特に相続の準備はしていなかったのです。
 ライフプラン
ライフプラン
生命保険に支払った保険料は
生命保険料控除として所得から控除される制度があります。
平成23年12月31日以前に加入した保険と平成24年1月1日以降に加入した保険で控除額が異なります。前者の場合、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の2区分が対象となります。年間保険料が100,000円を超えると最高額の控除を受けることができます。
 税制改正
税制改正
年末調整とは、その年の1月~12月までの1年間に支払われた給与に対し、 その給与から天引きされた源泉所得税の過不足額を12月に調整する仕組みのことです。 平成30年からの年末調整では、配偶者控除・配偶者特別控除の税制改正の影響を受けることになります。
 税務申告
税務申告
今年も年末まで2ヶ月を切り、年末調整の時期になりました。すでに会社から年末調整関係の記入を依頼されている方もいらっしゃると思います。昨年度の税制改正により、平成30年の年末調整はこれまでとは違う点がいくつかあります。ここでは、平成30年の年末調整の主な注意点を紹介します。
 お役立ち情報
お役立ち情報
厚生労働省が発表した8月の有効求人倍率は1.63倍にもなりました。有効求人倍率とは、ハローワークで仕事を探す人1人に対して、企業から何件の求人があるかを示しているものです。1.63倍の競争率ということになります。かなりの売り手市場です。バブル期を上回り、実に43年ぶりの水準だそうです。
 税務申告
税務申告
10月1日から健康保険の扶養認定の手続きが厳格化されました。健康保険組合の一部では、すでに同様の確認手続きがなされていますが、今後、協会けんぽにおいても行なわれます。
 建設業許認可
建設業許認可
建設産業に従事する方々が日々の業務に関わる法律を解説します。
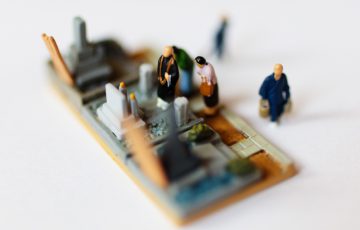 お墓
お墓
今、お墓のことと言ったらやはり「改葬トラブル」でしょうね。
先祖代々のお墓が、東北や四国や九州にある方はたくさんいらっしゃいます。でも住んでいるのが都心だとすると、たとえ納骨出来たとしてもその後のお参りは大変です。
 労務管理
労務管理
厚生労働省より「平成29年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。 全国的な労働相談の統計では最大規模の調査です。「個別労働紛争解決制度」とは、 個々の労働者と事業主との間で労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、 早期に解決を図るための制度です。
 労務管理
労務管理
引き続き中小企業の「人手不足」が深刻化しています。 ほとんどの中小企業では、欲しい人材がなかなか採用出来ない状況が続いています。 求人サイトや媒体などに数十万円、数百万円をかけたけど、なかなか応募者が来ないという話をよく耳にします。 応募者を増やすには、魅力的な会社作りが必要なのは言うまでもありませんが、「現在の会社の魅力をいかにして伝えるか」、というのも求人活動では重要なポイントになります。
 生前整理
生前整理
葬儀で困った人の話は大変多く聞かされますが、大切な方が亡くなられて、 ただでさえ気持ちが動転していて冷静になるのも大変なのに、
決めなければならないことの何と多いことか…
よく言われる「悲しむひまもない」とは、その状況をよく表した言葉だと思います。
その葬儀ですが、今ではその形もとても多様化しています。
ほんの一昔前は殆どの場合が、いわゆる一般葬でそれが普通の葬儀という感覚でしたが、
現在は家族葬を選ぶ方(ご家族)もだいぶ増えているようです。
 お役立ち情報
お役立ち情報
一般的な世界地図はメルカトル図法という方法で描かれており、球体である地球を無理やり平面に広げた描写のため、北極南極に近いほど大きく描かれてしまうという欠点と、地図作成国が中心になっているため、日本の世界地図の場合はアメリカとヨーロッパの距離感が分かりづらいという特徴があります。