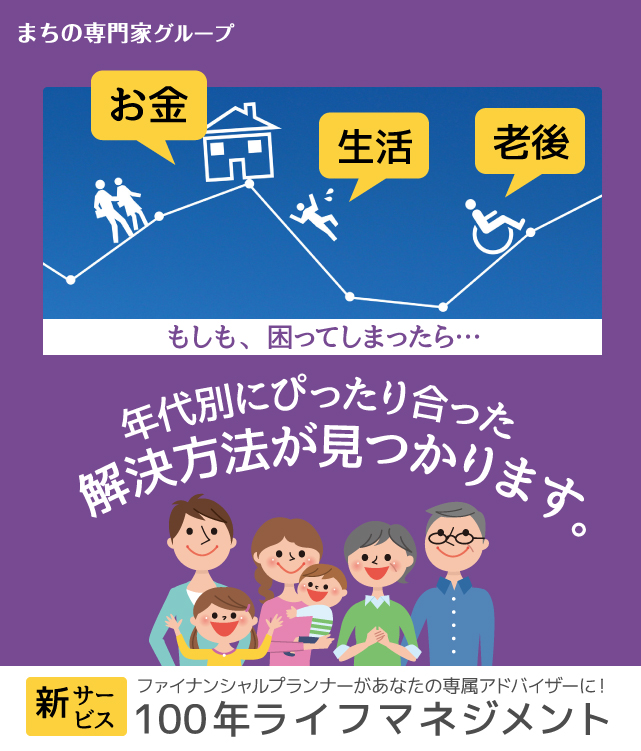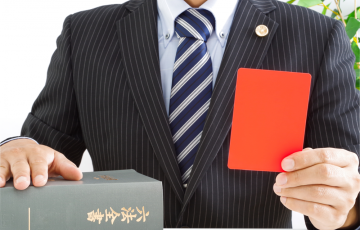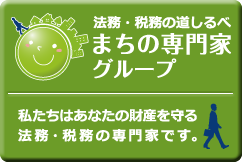令和6年の民法改正により、共同親権制度が導入されました。
そして、令和8年にはこの制度が施行される予定です。
この制度の導入により、今後どのような影響が考えられるのかをお話ししたいと思います。
親権とは
親権とは、親が子どもに対して有する権利のことを言います。
具体的には、子ども名義の財産を管理し、居所を指定したり、進学先などを選択したりなどという権利があります。
なお、以前の民法には親権として懲戒権などが存在していましたが、子どもの人格尊重などの点からこういった権利は削除されました。

これまでの単独親権の制度
現在の制度では、婚姻期間中は夫婦が共同して親権を有し、離婚後は単独親権となります。
親権者を父母いずれにするかについては、離婚時に必ず決めなければなりません。
親権者の選択は、協議ができれば協議により、協議により決められない場合には裁判所が決めることになります。
その際には、子どもの福祉の観点から選択されることとなり、父母どちらが子どもと一緒に生活しているのか、子どもの年齢や兄弟の状況、各親の状況や子どもの養育に関する意向などを踏まえて決められます。
現行の制度では、親権者をいずれにするかで大きな紛争になることが多く、また、離婚後に一方の親が適切に子どもの養育に関われないなどの問題も指摘されていました。
そもそも、日本以外の多くの国では共同親権制度を採用しているところが多いということもあり、今回の民法改正により共同親権が導入されることとなったのです。

共同親権制度とは
① 改正法では、単独親権とするか共同親権とするかを選択することが可能です。
そのため、夫婦が離婚時に共同親権とすることを選択することで共同親権制度を利用することができます。
また、夫婦間で共同親権制度に合意されない場合であっても、共同親権とすることが相当な理由がある場合には、裁判所が共同親権とすることを判断することもあります。
なお、虐待やDVのおそれがあるような場合には、裁判所は必ず単独親権を選択することとされています。
② 共同親権となる場合、子どもの生活に関わる事項(教育、進学、医療など)については、父母で話し合い、合意形成を図ることが求められます。
なお、共同親権の場合であっても、日常の行為(食事や服装の決定や短期間の旅行など)や子どものために急迫の事情があるとき(緊急の医療行為など)については、単独で親権を行使することができます。
合意ができれば、その内容で親権を行使することになります。
意見が対立した場合は、裁判手続を使い、家庭裁判所が子どもの利益を考慮して、父母の一方を当該行為の親権行使者として指定することになります。
③ 共同親権となった場合であっても、その後の状況に変化があった場合(例えば一方の親からの虐待など)には、親権者が変更されることもあります。
④ 共同親権制度を用いることで、これまでに比べて面会交流が円滑になることが期待されています。
(これまでは、親権者となった親が他方の親と子どもの面会交流に抵抗を示し、実現されないケースも多々ありました)
面会交流が制限されることで、養育費の不払いが発生するケースも減少すると考えられており、こういった面からも共同親権制度のメリットがあると指摘されています。

制度導入後の影響
このように、共同親権制度の導入はこれまでとは大きく異なる制度を取り入れることとなります。
共同親権となることで、より子どもの養育にとって良いものとなる可能性もありますが、進学や住居の選択などについて共同親権者がうまく協議ができないような状況になりトラブルとなるなど、今後どのように運用されるのかは不透明なところも多数あります。
共同親権のいいところを踏まえながら、今後の動向を注視していくことが重要でしょう。
離婚の際には親権の問題も大きいので、弁護士など専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。
投稿者プロフィール

- フットワークのよさに定評のある40代の弁護士4名からなる法律事務所です。専門・得意分野が幅広いことも強みの一つ。分野の異なる法律事務所で研鑽を積み、税理士等他士業と連携体制も取れております。また、セミナーや講演も積極的に行い、良質なリーガルサービス実現を目指しております。事務所は、交通の便が良いターミナル駅JR・東急各線「武蔵小杉駅」から徒歩5分。首都圏エリアのご相談可能です。
最新の投稿
 トラブル・訴訟2026年2月16日【無償の法的支援】弁護士の被害者支援制度がスタート
トラブル・訴訟2026年2月16日【無償の法的支援】弁護士の被害者支援制度がスタート 共同親権2025年7月3日【共同親権】制度導入後、子育てにはどんな影響が?
共同親権2025年7月3日【共同親権】制度導入後、子育てにはどんな影響が? トラブル・訴訟2024年10月17日【過失割合】交通事故に遭った場合、ドラレコがあると有利?
トラブル・訴訟2024年10月17日【過失割合】交通事故に遭った場合、ドラレコがあると有利? トラブル・訴訟2024年6月18日【AIと著作権】AIが作った絵画や音楽は著作権を侵害する?
トラブル・訴訟2024年6月18日【AIと著作権】AIが作った絵画や音楽は著作権を侵害する?
100年ライフマネジメント
月々1000円(税込)で専属アドバイザーには何度でもご相談いただけます。